こんにちは。れいるです。
受験生時代、社会保険労務士と検索すると、検索候補に「やめとけ」という言葉がでてきて、不安に思うことがありました。
今こんなにも頑張って勉強しているにも関わらず、やめとけなんて言われたら、頑張って合格することに意味があるのかなとか考えてしまいますよね。

しかし、私は決して「やめとけ」なんて思いません。
社会保険労務士の資格は、いま活かせなかったとしても一生ものですし、将来の可能性を広げてくれる素晴らしい資格だと思っています。
そこで、よく「社会保険労務士はやめとけ」と思われている理由は何なのかを挙げて、それに対してやめとけと思うことはない理由についてお話していきます。
社労士試験の難易度が高すぎる
社労士試験は、合格率が毎年一桁台である超難関資格です。
(ちなみに私が合格した令和6年度の合格率は、6.9%でした。)
その為、簡単には取得できませんし、勉強するにも相当の覚悟は必要です。
勉強していると、「ここまで時間を使って勉強していても、合格できるのか?」なんて思ってしまうこともあるかもしれません。
しかし、社労士試験は頑張れば頑張るほど答えてくれる試験ですし、私のようにそんなに良い学歴がない者でも合格できるチャンスはあります。
合格率が低いことには理由がありますので、その理由についてまとめた記事がありますのでご参考に掲載します。
また、勉強方法についてはただ単にガムシャラに頑張って勉強すればいいということはありません。
社労士試験の勉強方法には、コツがありますので、ぜひ私の勉強方法を参考にして頂き、無駄のない勉強方法で進んでいただければ幸いです。
■選択式のオススメ勉強方法
■択一式のオススメ勉強方法
会社員として資格の活かし方が分からない
社労士=開業というイメージが強いこともあって、会社員としては資格の活かし方が分からないこともあるのではないでしょうか。
しかし、社労士資格を取得しても会社員は辞めたくないと考えている方であっても、資格を活かすことは可能です。
では、実際にメリットがあると考えられる理由についてお話します。
人事や総務に異動できる可能性がある
社内の人事や総務に異動したいけれど、異動させてくれないというお悩みがある方にも、社労士資格は活かせる可能性があります。
また、職場での不満を抱えている場合、部署異動をすることで解消できることもありますので、社労士資格を使って異動の機会をつくるきっかけにもなります。
社労士資格は、難関資格であることが分かっている人事決定権のある方がいれば、人事や総務に異動してもらうことで社内の士気アップにもつながるメリットがあると考えてもらえるでしょう。
万が一、社労士資格がよく分かっていない者であれば、合格率の低さから難易度が高いことを説明し、ご自身が人事や総務に異動することでどんなメリットがあるのか説明してアピールしてみましょう。
社労士事務所に転職できる可能性がある
せっかく社労士試験に合格できたら、実際に社労士として働きたい気持ちが出てくることでしょう。
雇われで社労士を目指すのであれば、社労士事務所への転職がおすすめです。
実際、社労士事務所の求人を見ていると、無資格者でも採用している場合もある為、資格を取得していることはかなりのアピールポイントになると考えられます。
また、社労士事務所は個人で経営されている方もいる為、求人が実際あるのかどうかもお悩みポイントとなるかもしれませんが、法人事務所であれば求人は出ていることはよくあります。
私は、社労士試験合格後、試しに「ビズリーチ」に登録してみましたが、社労士法人からのスカウトメールが何通か届きました。
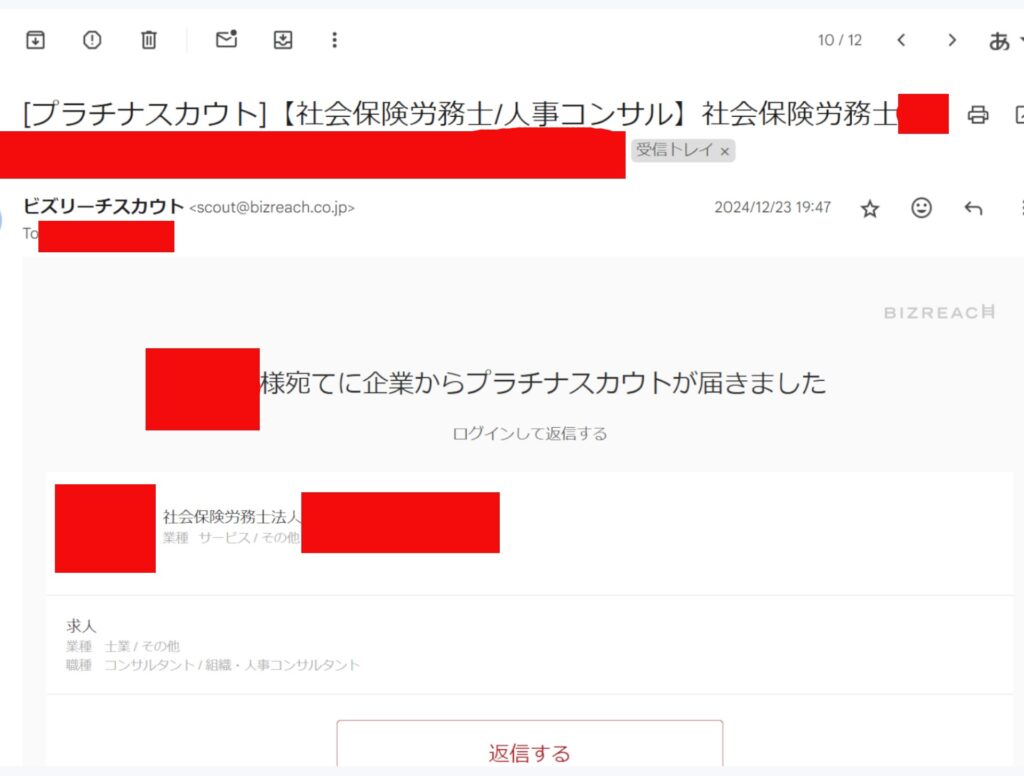
その他、地元の小規模な事務所であれば、広告求人を出す費用もかかる為、ハローワークやインディード、民間の求人広告サイトなどに掲載されている可能性があります。
社労士事務所への転職も1つの可能性として、ぜひ資格取得後の目標にしてみてくださいね。
勤務社労士登録するとメリットがたくさんある
私は現在、社労士事務所とは関係のない業種(福祉関係)で、勤務社労士登録をしています。
登録に至るまでは、職場との交渉であったり、登録料や毎月の会費がかかってくる為、当初は登録するかどうか悩みました。
しかし、社労士の先輩に相談したところ、登録にはたくさんメリットがあった為、登録することにしました。
以下、私が登録してよかったなと感じてる点についてお話します。
社会保険労務士と名乗ることができる
社会保険労務士と名乗る為には、社会保険労務士試験に合格後、都道府県社会保険労務士会(以下、労務士会)を経由して全国社会保険労務士会連合会に登録しなければなりません。
登録せずに社会保険労務士を名乗ることは、社会保険労務士法違反となり、100万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
登録しない場合、「社会保険労務士試験の合格者」となる為、社会保険労務士ではないということになります。
せっかく難関資格を取得したからには、社会保険労務士であることを名乗りたいですよね。
開業は厳しいけれど、会社員でありながら実務を行う社会保険労務士として名乗りたい場合は、勤務社労士登録をぜひ検討してみてください。
社会保険労務士会の研修を受けることができる
労務士会では、頻繁に研修を行っています。
私が所属している大阪府社会保険労務士会では、新規入会者向けの研修も用意されていて、資格試験に合格してまだ社労士としてやっていけるかどうか不安という悩みも解決してくれるような研修があります。
また、実務では労働関係はやっているけれど、年金はまだ初心者で‥という方向けに、年金に特化した研修もあり、自分に足りないと思う研修を選択しながら身に着けていくことができます。
労務士会によって、研修内容は様々ですので、複数の都道府県で悩んでいる場合は、入会する前に各労務士会がどのようなことを行っているのか調べてから入会することをオススメします。
社労士との交流ができ人脈を広げることができる
私は、受験生時代は通学で学んでいましたが、結局誰とも知り合うことなく卒業してしまい、社労士の知り合いがまったくいない状態でした。
また、将来的には開業を目指しており、その為にも人脈を作っておかなければと思い、入会を決めました。
労務士会に入会すると、研修のほか支部の交流会にも参加できますので、社労士の先輩方とお話できるチャンスがあります。
私のように将来開業を目指したいという方ほど、開業登録でなくとも、まずは勤務やその他登録で入会して人脈を広げていくことをオススメします。
一部事務の省略をすることができる
社労士事務所に勤めていなくとも、会社員で実務を行っている方であれば、勤務社労士として登録した後、労務士会を通じて労働局に申請することで、雇用保険関係手続に係る照合省略を行うことができます。
参考:厚生労働省愛知労働局『確認書類の照合省略に係る申出について』
例えば、離職証明書を作成する際、賃金台帳やタイムカードなど添付書類が必要となりますが、これらを省略することができます。
(ただし、新規入会者は、届出実績が必要です。)
少しでも業務の効率化ができれば、実務担当者としては嬉しいですよね。
※一部、省略不可な書類もありますので、申出した際は後に送付される通知書をご確認ください。
開業しても廃業するリスクがある
社労士試験合格後に開業したい!と考えている方は、結構いらっしゃるかと思います。
会社員を辞めて、憧れの個人事業主なんて夢を描いている方もいらっしゃることでしょう。
しかし、開業しても上手くいくのかどうか・廃業してしまうのではないかと不安に思うこともあります。
とは言っても、現代社会では様々な働き方があって、社労士1つに絞る必要はないと思っています。
副業として社労士を行うもよし、逆に社労士を本業として他にアルバイトなど副業するもよし。
社労士の開業方法は考え方次第で働き方は自分次第です。
その他にも、定年後の保険として、資格を取っていれば、定年退職で職を失っても開業社労士をしながら年金生活を送るなんてことも可能です。
では、詳しく1つずつ解説していきます。
副業で開業社労士として活動する
会社の就業規則等で、副業が禁止されていなければ、現職を続けながら開業社労士を行うことができます。
但し、会社によっては副業の内容によって申請が通らないなどルールがある可能性がある為、会社には確認するようにしましょう。
開業社労士登録を行うと、労務士会ホームページに名前や住所など事務所情報が公開される為、会社に内緒で登録することはオススメしません。
開業登録することで、社労士として働くことの意識アップにもつながりますし、会社にも社労士として活躍する社員がいてくれることのメリットを感じてもらえれば、登録を許可してもらえるかもしれませんのでぜひ交渉してみてください。
社労士1本だけにこだわらず他の仕事を組み合わせて働く
開業社労士は、社労士だけでやっていかなければならないということはなく、社労士を本業としながら他で働くという働き方もできます。
例えば、社労士以外にも実は働いてみたい仕事があって、だけど本業としては稼げなさそうなジャンルにもチャレンジすることができます。
また、社労士を本業にしつつも、他ではアルバイト程度の責務で気楽に働きたいという組み合わせも有りです。
今の時代、働き方は多様化していますので、1つの場所で正社員で働く・個人事業主だけで働くといった固定概念にとらわれず、ぜひどんな働き方があるのか検討してみてもいいのかもしれません。
定年退職後に年金の足しになるよう開業社労士として仕事する
将来もらえる年金について、生活していけるかどうか不安に思うこともありますよね。
会社も終身雇用を行っているところは少なく、定年になれば職を失うことになります。
そこで、今からでも何か手に職をつけていれば、安心できるのではないでしょうか。
社労士の開業には年齢制限がなく、資格があって登録さえできれば、いつでも開業できます。
年金だけでは生活できないと思う方には、ぜひ社労士資格の取得をオススメします。
社労士試験に合格したことが将来の自信につながる
最後に、社労士試験という難関資格に合格したということは一生の自信につながっていくことがメリットとしてあることをお伝えします。
これまでの人生を振り返って、学歴コンプレックスがあったり、誇れるような実績もない方であれば、なおさら社労士試験に合格することで自分の人生に大きな自信をつけるチャンスであると思っています。
複数回受験の方からすると、毎年毎年ダメでそろそろ諦めようかなと思ってしまうこともあるかもしれません。
諦めるという選択肢も必要ではありますが、何か変えたい・これまでの自分は嫌だと思うのであれば、チャレンジし続けることで、見えてくる景色があると思っています。
また、これはあくまで私の考えですが、社労士試験を受験される方の中には、資格の特徴から「人を助けたい」と思っていらっしゃる方が多いように感じます。
この頑張りをいつか誰かの為に活かせれば…思うことができれば、きっと将来人間として成長させてくれるに違いありません。
ですので、特に社労士資格を仕事に活かす予定がない方であっても、合格することで成長した自分に出会うことができるメリットがあります。
ぜひ、合格を諦めそうになった時は、こういった視点もあるのだなと思い出してもらえれば幸いです。
社労士資格は一生もの!将来を見据えて資格取得がオススメ!
社労士資格を取っても意味がないからやめとけといった声は、インターネットの中で見かけることはあります。
しかし、実際に社労士として活動している方や合格された方の話を聞いていると、「社労士資格が活きているな」と感じることがあります。
実際、今回お話した内容は、私が出会ってきた社労士の方・合格者の方からお話をお伺いしたことを参考に紹介している部分もあります。
社労士資格を活かせている方は、開業の方、勤務の方、登録せずとも今の会社で頑張っている方、いろんな方がいらっしゃいます。
資格の活かし方は人それぞれですし、開業登録が正しいとかそうでないとかはありません。
現在、社労士資格を目指して頑張られている方が目標を見失ってしまいそうになった時、合格した後を考えることがとても大事です。
漠然とした目標でもいいので、社労士はやめたほうがいいと思わず、未来があるのだと信じて、社労士資格取得をぜひ目指してみてください。
社労士試験についてご相談承ります あなたのお悩みを共有して一緒に考えていきませんか?
